-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
2025年10月 日 月 火 水 木 金 土 « 9月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
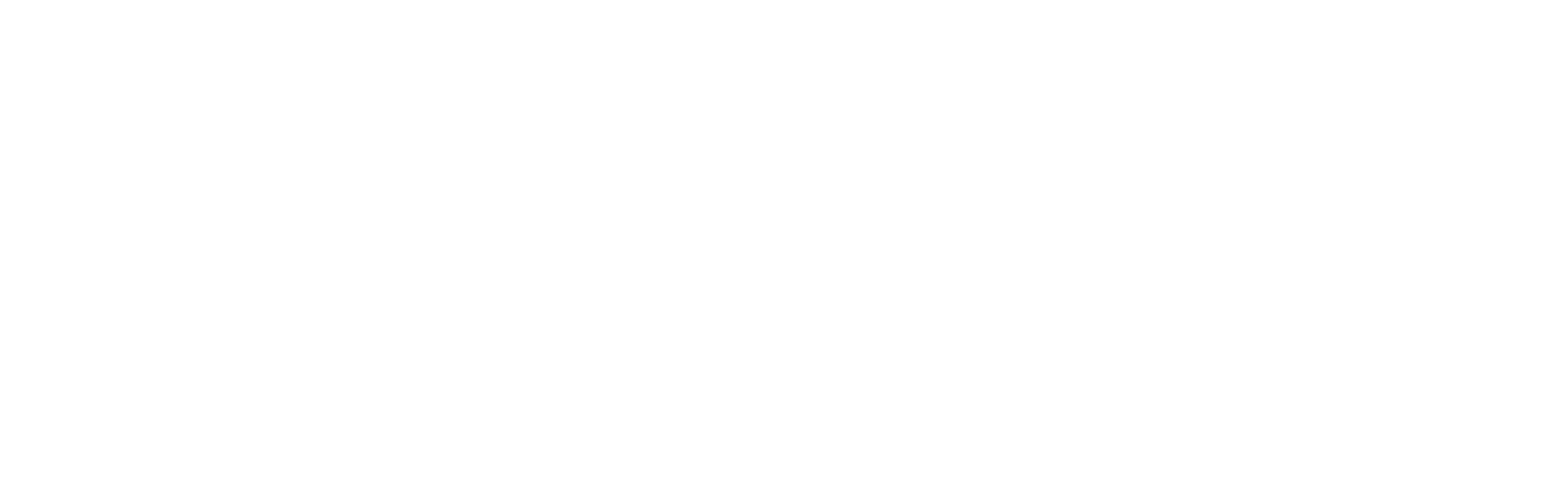
皆さんこんにちは
中野防水の更新担当の中西です。
「雨漏り」は“現象”であって“原因”は一つではありません。素材・納まり・経年・使用環境が連鎖して起こる“合成リスク”です。本編では、どこから水が入り、どう留め、どう管理するかを“現場で役立つ順番”で解説します。
1. 防水の役割—構造を濡らさないという設計思想
建物の耐久性は「構造体を濡らさない」ことに尽きます。鉄筋コンクリートは中性化を早め、鉄骨は腐食、木造は腐朽菌・シロアリのリスクが高まります。防水は一次防水(仕上げ)と二次防水(下地・防水層)の二重で考えると理解が早いです。屋根・屋上・バルコニー・開放廊下・浴室のような“常時濡れる場所”は、二次防水(主防水)が主役、サッシ・外壁のような“雨仕舞い中心の場所”は一次防水(仕上げ+板金)を確実にしつつ、二次防水でバックアップする設計が基本です。
2. 雨水が入る“道”を知る—面・線・点 の3分類
雨水の侵入は大きく以下の3つに分解できます。 – 面(面状):屋上スラブやバルコニー床など、面全体からの浸透。微細なクラックや防水層の劣化、膜厚不足で起こります。 – 線(線状):シーリング目地、立上りと床の取り合い、笠木ジョイントなどの“線”。動き(伸縮・温度差・風荷重)に追随できず、微開で漏水。 – 点(点状):ドレン、配管貫通部、ビス穴、釘孔、手すり支持金物など。小さな穴1つで大量に入ります。
✅ 現場メモ:調査は「面→線→点」の順で広い方から狭い方へ。散水試験も上流→下流の順。先に“点”だけ塞ぐと、別経路の再現性が消えて原因特定を誤ります。
3. 物理現象を押さえる—負圧・毛細管現象・水の滞留
• 負圧吸引:台風時、風で外壁表面が負圧になり、風下側の隙間から室内方向へ水が吸い込まれます。見た目「逆流」に注意。
• 毛細管現象:0.1〜0.3mmの微細な隙間でも水は横移動します。仕上げの重なり向き・端末の折返し・差し込み寸法が重要。
• 滞留:勾配不足で水が溜まると、紫外線+熱で防水層が劣化加速。藻・埃堆積→微細なピンホール→雨量ピークで漏れる、の流れに。
4. 防水工法の全体像—“正解”は一つじゃない
代表的な工法の性質を改修目線で対比します。 – ウレタン塗膜防水(密着/通気緩衝):複雑ディテールに強い。連続被膜で継ぎ目が少ない。含水下地は通気緩衝で逃がす。膜厚管理が命。 – FRP防水:軽量・硬質、ベランダで定番。立上りの折返しが取りやすい。下地動きにやや弱いのでジョイント処理に配慮。 – シート防水(塩ビ・ゴム・TPO):工場製の品質が担保される。溶着・機械的固定で施工スピード◎。複雑形状は納まり検討を厚めに。 – アスファルト防水:信頼性が高く長寿命。熱工法は管理と安全対策が必須。大型屋上や長期保全計画で有力。⬛
選定の軸:①下地の含水・動き②ディテールの複雑さ③既存防水の種類④改修時の騒音・臭気制限⑤歩行・荷重 ⑥予算と保全計画。
5. 現場フロー—“段取り八分”の型
1. 事前調査:図面・改修履歴・保証書・漏水履歴を収集。含水率・打診・赤外線・散水の順で仮説を立てる。
2. 仮設・安全:転落・開口・火気・動線分離。住戸・テナントへの告知。養生計画は“水の流れ”も想定。
3. 下地補修:爆裂・脆弱部除去/クラック注入/不陸調整/勾配形成。仕上げの前に水がたまらない形を作る。
4. プライマー:素材・含水率・温湿度で選択。可使時間・塗布量を守る。養生期間は焦らない。
5. 主防水:工法に応じて膜厚・重ね幅・溶着条件を数値で管理。小口の端末と立上りに時間を配分。
6. 端末・役物:ドレン、改修用ドレン、脱気筒、笠木取合い。“出口”の確実性=長寿命。
7. 検査・記録:中間検査→是正→最終検査。写真・膜厚計・溶着試験片・含水ログを残す。
8. 引渡し・保証:使用上の注意、清掃・点検周期、保証範囲。アフター点検の期日を契約書に明記。
6. よくある誤解—“塗れば止まる”は危険 ⚠️
• 原因不明のまま全面塗り:再発時に原因追跡が困難。調査費用の“節約”が、後の手戻りコストを増大させます。
• ドレン未改修:既存ドレンの不良を放置して表面だけ更新。漏水は“面”よりも“点”からが多い。
• 立上りの折返し不足:最低でも規定高さ(一般に150mm目安、外部は200mm推奨ケースも)を確保。掃き出しサッシ下端が低い場合は特別納まりを設計。
• 乾燥不十分:含水を閉じ込めると膨れ・剥離。通気緩衝・脱気筒・天候待ちの判断がプロの差。
7. チェックリスト—着手前5分で安全・品質UP ✅
☐ 図面・改修履歴・漏水マップの入手/共有
☐ 勾配・滞水箇所・ドレン機能の確認
☐ 含水率・温湿度の計測と記録
☐ 仮設転落防止・立入禁止・火気許可の整備
☐ 下地補修範囲の合意(写真+数量)
☐ 端末・立上り・役物の納まり図承認
☐ 膜厚・溶着・重ね幅等の検査基準設定
☐ 中間・完了検査のスケジュール化(関係者同席)
8. ケーススタディ—ベランダ“点漏水”を止める
症状:大雨と強風時のみ、窓際の天井にシミ。通常雨では無症状。
仮説:サッシ周りの線状・点状の複合。風圧でサッシ下端から吸引→バルコニー床の勾配不足で滞水→ドレン周りの防水端末が弱点。
対策: 1. サッシ両端の目地を撤去・再シール(二面接着・背面材管理)。 2. バルコニー床は通気緩衝ウレタンで再防水、立上り200mm確保。 3. 既存ドレンに改修用ドレンを挿入+フランジ溶着。脱気筒を新設。結果:散水再現なし。台風時も無事。原因は“点”+“滞留”の相乗でした。
9. コスト・耐用年数・ライフサイクル
• 耐用年数は“材料寿命×使用環境×メンテ”の掛け算。直射日光・滞水・歩行荷重・塩害・寒冷地は劣化促進。
• 見積比較は単価だけでなく、下地補修・端末金物・改修ドレン・脱気・検査記録・保証条件まで総額で。
• 提案の良し悪しは“ディテール図の有無”と“検査の数値化”。図と数値が弱い見積は、再発リスクを価格に転嫁していない可能性。
10. FAQ よくある質問 ♀️
Q1. 雨漏り箇所の真上を直せば止まりますか?
A. いいえ。水は“上流”から回り込みます。調査は広く、対策は上流から。
Q2. 梅雨時は施工できますか?
A. 可能な工法もありますが、乾燥・養生時間を厳守。通気緩衝×脱気でリスク低減。天候リードタイムを計画に組み込みましょう。⛅
Q3. どの工法が一番長持ち?
A. 条件次第。大型屋上ならシート・アスファルト、複雑なベランダならウレタンが有利など、“適材適所”が最長寿命の近道。
11. まとめ—防水は“水のデザイン”
目に見える仕上げよりも、水の入り方・流れ方・出し方をデザインするのが防水です。原因を面・線・点で分解し、上流から順に潰す。勾配とドレンを整え、端末・立上りを丁寧に。数値で検査し、記録を残す。これが“雨漏りゼロ設計”の基本形です。
次回予告(概略):「下地調査と雨漏り診断」—赤外線は“万能の証拠”ではありません。目視→打診→含水→赤外線→散水の順で仮説検証。散水は上流から、写真と計測値で“再現性”を記録します。
________________________________________
お問い合わせ・ご相談 ✉️
「自宅や物件で雨漏りが不安」「見積を比較したい」「図面上で納まりを検討したい」など、お気軽にご相談ください。現場で使えるチェックリストやディテール図のひな形もご用意できます。✨